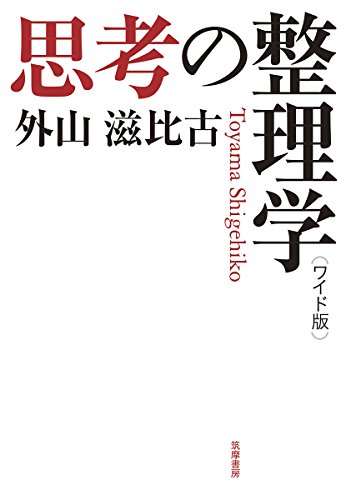思考の整理学。なぜ?と問える人になるために

要約
『思考の整理学』のポイント
飛行機「すぐれた問題作成の力があり。なぜ?と問える」
本書の目的は「問題作成能力に秀でた人間になるための心がけ」を説くもの。ノウハウ本ではなく抽象的な考え方を取り扱ったものだ。
「教えない」ことがいいこともある。漢文の素読のように、内容を教えずただ音を読ませることで、それはどういう意味なのか?とモチベーションが生まれる。今の学校教育は好奇心をはたらかせる前に意味を押し付けている。
朝の頭はとても能率がいい。これを前提として朝の最適化をはかっている著者。
・素材+酵素+寝かせる=秀でたテーマ
例)「シェイクスピアの評価」 (素材)+「人間は自分の解釈を作ろうとする」(醗酵)+「デマの真理」(醗酵)+2.3年寝かせる=異本論
素材は同類のものから
酵素は同類ではなく異質なものから持ってくる。
ぼんやりしていたのでは何も出てこない。いつも心に考え事があるから着想が生まれるのだ。とはいえ『見つめる鍋は煮えない』という言葉があるように、注意しすぎていてもよくない。
独創的な思考を生み出す条件→「自分の頭で考え出した、他の追随を許さない(少なくとも本人が自覚する)着想」が必要。
その上で「諸説を照合」し「すべてを認めて」、「調和」させるのが、独断に陥らず手堅い"カクテル論文"である。
知のエディターシップ――広義の編纂――もっている知識をいかなる組み合わせで、どういう順番に並べるかが重要。ABCDではおもしろくないが、EBADだと面白いということがあり得るように、"順序"を並べ替えることは大事である。着想もまたその対象になりうる。
思考の整理とは、いかにうまく忘れられるかである。
メタ・ノート―アイディアを書き出すノート、そしてそこから期待ができるものをこのノートに移し替えるのは、土を変えることで、新しい生命の展開を期待できるからだ。コンテクストの遇、不遇がある。
文章上達の秘訣三か条『三多』
・多くの本を読むこと
・多く文を作ること
・多く工夫し、推敲すること
人間には、グライダー能力と飛行機能力とがある。受動的に知識を得るのが前者、自分でものごとを発明、発見するのが後者である。両者はひとりの人間の中に同居している。グライダー能力をまったく欠いていては、基本的知識すら習得できない。何も知らないで、独力で飛ぼうとすれば、どんな事故になるかわからない。
しかし、現実には、グライダー能力が圧倒的で、飛行機能力はまるでなし、という"優秀な"人間がたくさんいることもたしかで、しかも、そういう人も"翔べる"という評価を受けているのである。
――グライダーP13
いわゆる学校のない時代でも教育は行われていた。ただ、グライダー教育ではいけないのは早く気がついていたらしい。教育を受けようとする側の心構えも違った。なんとしても学問を^したいという積極性がなくては話にならない。意欲のないものまでも教えるほど世の中が教育に関心をもっていなかったからである。
そういう熱しな学習者を迎えた教育機関、昔の塾や道場はどうしたのか。
入門しても、すぐ教えるようなことはしない。むしろ、教えるのを拒む。剣の修行をしようと思っている若ものに、毎日、薪を割ったり、水をくませたり、ときには子守までさせる。なぜ教えてくれないのか、当然、不満をいだく。これが実は学習意欲を高める役をする。
――不幸な逆説.P17
こういう考え、着想をもつと、どうしても独善的になるものらしい。ほかの考えはすべてダメなもの、間違っていると感じられてくる。自信をもつというのはいいが、行きすぎれば、やはり危険である。ひとつだけを信じ込むと、ほかのものが見えなくなってしまう。
アメリカの女流作家、ウィラ・キャザーが、
「ひとりでは多すぎる。ひとりでは、すべてを奪ってしまう」
ということを書いている。ここの「ひとり」とは恋人のこと。相手がひとりしかいないと、ほかが見えなくなって、すべての秩序を崩してしまう、というのである。
着想、思考についても、ほぼ、同じことが言える。「ひとつだけでは、多すぎる。ひとつではすべてを奪ってしまう」
――カクテルP42
話してしまうと、頭の内圧がさがる。溜飲をさげたような快感がある。すると、それをさらに考え続けようという意欲を失ってしまう。
あるいは、文章に書いてまとめようとい気力がなくなってしまう。しゃべるというのが、すでにりっぱに表現活動である。それで満足してしまうのである。あえて、黙って、表現へ向かっての内圧を高めなくてはならない。
――しゃべるP156
A読みをしていたのが、突如としてB読みのできるようになるわけがない。移行の橋渡しがなくてはならない。それに役立つのが文学作品である。国語教育において、文学作品の読解が不可欠な理由がそこにある。
物語、小説などは、一見して、読者に親しみやすい姿をしている。いかにもA読みでわかるような気がする。あまり難解であるという感じも与えない。それでは創作がA読みでだけであることがうすうす察知される。このとき、読者は既知に助けられ、想像力によって既知の延長線上に新しい世界をおぼろげにとらえる。こういうわけで、同じ表現が、Aで読まれるとともに、Bでも読まれることが可能になる。創作が独特のふくみを感じさせるのは、この二重読みと無関係ではあるまい。
実際には、しかし、このように簡単にAからBへの移行が行わてはいない。きわめて多くの読みの指導が、B読みを可能にしないまま、浅い意味での文学読者を育てるに終わってしまっているのである。
(中略)読みは創作の理解が終点であっては困る。本当にBの読みができるようにするのが最終目標でなくてはならない。
それには、文学作品を情緒的にわかったとして満足しているのではなく、"解釈" によって、どこまで既知の延長線上の未知がわかるものか。そのさきに、想像力と直観の飛翔によってのみとらえられる発見の意味があるのか。こういうことがしっかり考えられていなくてはならない。
――既知・未知 201~202
本を読むにしても、これまでは "正解" をひとつきめて、それに到達するのを目標とした。その場合、作者、筆者の意図というのを絶対とすることで、容易に正解をつくり上げられる。それに向かって行われるのが収斂的読書である。
それに比して、自分の新しい解釈を創り出して行くのが、拡散的読書である。当然、筆者の意図とも衝突するであろうが、そんなことにはひるまない。収斂派からは、誤読、ほかいだと避難される。しかし、読みにおいて拡散作用は表現の生命を不屈にする絶対条件であることも忘れてはなるまい。古典は拡散的読みによって形成されるからである。筆者の意図がそのままそっくり認められて古典になった作品、文章はひとつも存在しないことはすでにのべたとおりである。
――p208
かつて日本人の科学論文を英訳する仕事をしていたイギリスの物理学者がわれわれの虚を衝く問題提起をしたことがある。日本人の論文には「であろう」という文待受がしばしばあらわれる。「AはBである」とすべきところが「AはBであろう」となっている。これではいかにも自説があやふやで、自信がないように聞こえる。ところが本当は論拠が不確かであったりしているわけではなく、「AはBである」と同じ内容をもっている。それなのに「AはBであろう」としてある。こういう「であろう」は英語に相当するものがない。どう訳したらよいのかという一種の告発であった。
――文庫文のあとがきにくわえてp219